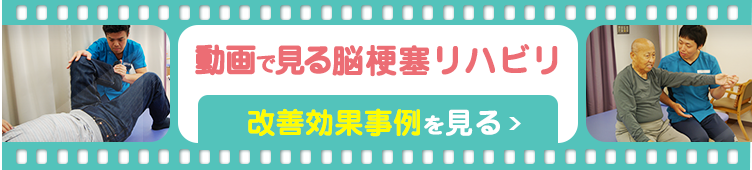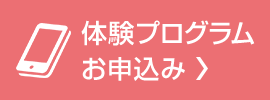お知らせ
脳梗塞リハビリBOT静岡のお知らせを随時更新していきます。
2025.08.07 脳梗塞関連グッズ
脳梗塞後の痛みはリハビリで軽減できる?原因と対処法を徹底解説

脳梗塞の後遺症として代表的なもののなかに、「痛み」があります。痛みは本人にしかわからない辛いものですが、日常生活に支障が出るケースも少なくありません。この記事では脳梗塞後の「痛みの原因」や「対処方法」について詳しく解説します。
目次
脳梗塞の後遺症として起こる「痛み」とは

脳梗塞とは、脳への血流が一部途絶えることで脳が損傷する疾患です。脳が損傷するために生じる症状としては、
・運動麻痺
・言語障害
・感覚障害
・認知障害
・痛み
などといった症状があります。このうち、脳梗塞後の痛みは神経が原因となる「中枢性疼痛」と、筋肉や関節・姿勢などが原因となる「末梢性疼痛」に大別されます。次項以降で解説しますが、原因と対処方法が異なるため注意が必要です。
いずれにせよ、脳の損傷が原因で生じる症状であるため、多くの場合は回復が難しく、痛みも長期間続く可能性があります。その結果、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。日常生活を快適に過ごすためには、状況に応じたリハビリや福祉サービスの利用が重要となります。
脳梗塞後の痛みの主な原因

脳梗塞の後遺症としてある痛みは「中枢性疼痛」と「末梢性疼痛」に大別されます。それらは以下の3つの要素が原因です。
・神経因性疼痛(ビリビリ・ジリジリした痛み)
・痙縮・拘縮による筋肉や関節の痛み
・姿勢や運動制限による二次的な痛み
それぞれの原因によって痛みの出方・対処方法が異なるため、痛みを軽減するためにも原因をしっかりと理解しましょう。
神経因性疼痛(ビリビリ・ジリジリした痛み)
神経因性疼痛は、脳梗塞によって死滅した脳細胞が直接の原因となり、神経が障害されることで生じる痛みです。特徴的な症状としては、「ビリビリ」や「ジンジン」といったしびれるような痛みが多く見られます。死滅した脳細胞が原因であるため、治療が難しいことが知られています。
また、脳には痛みの信号を伝える際の中継地点として「視床(ししょう)」という部位があります。この視床が損傷を受けると、感覚信号が誤って伝えられ、触れただけで痛みが出たり、冷たい感覚が痛みに変わるなど、痛みの誤作動が起こるかもしれません。この症状は「視床痛」と呼ばれています。
| 痛みの特徴 | 内容 |
| 発症時期 | 数日〜数ヶ月後に発症することもある |
| 性質 | 焼けるような痛み、しびれ、電気が走る感じ、針で刺されるような痛みなど |
| 部位 | 脳梗塞によって障害(麻痺)された側の手足・体幹が多い |
神経因性疼痛や視床痛は通常のケガや炎症による痛みとは異なり、神経の障害によって生じる痛みであるため長く苦しめられる原因となる痛みです。原因である脳細胞は回復しないため、痛みの完治よりもリハビリなどによる痛みのコントロールに重きを置いた治療が重要となります。
痙縮・拘縮による筋肉や関節の痛み
脳梗塞の後遺症による痙縮(けいしゅく)や拘縮(こうしゅく)は、筋肉や関節に生じる障害で、「末梢性疼痛」に分類される痛みの原因となります。
痙縮とは、脳神経が死滅または機能しなくなることで、筋肉の固さを調整できなくなり、筋肉が常に緊張して固まってしまう状態を指します。
一方、拘縮は関節に生じる障害で、痙縮や麻痺によって長期間関節を動かせなくなった結果、関節が固まり動きが制限される状態です。
これらの痙縮や拘縮により筋肉や関節の動きが制限されることで、痛みが生じやすくなります。
| 痛みの原因部位 | 内容 |
| 筋肉 | 痙縮の緊張や拘縮による固まりによって筋肉が常に緊張し、 筋肉が疲労・酸欠状態になり、鈍い痛みを感じる。 また、急にストレッチをかけられることで生じる痛みもある |
| 関節 | 固まった関節を動かした時に 内部の組織がひっかかったり引き伸ばされたりして痛む |
また、固まった筋肉や関節に二次的な炎症が生じたり、筋肉が機能しないために脱臼を起こして痛みにつながるケースもあります。
姿勢や運動制限による二次的な痛み
脳梗塞による麻痺によって筋肉の機能やバランス不良が生じ、姿勢や運動制限が原因となる痛みです。筋肉や関節の痛みと同様、末梢性疼痛に分類されます。
| 痛みの原因 | 内容 |
| 姿勢 | 寝たきりや車椅子生活で褥瘡(床ずれ)や筋肉のこわばり、 血流低下・関節拘縮が原因となって生じる痛み |
| 麻痺による左右のアンバランス | 麻痺した側を麻痺していない健側で庇うことで、 健側の筋肉や関節に生じる関節炎や筋肉痛など |
| 運動障害による疼痛 | バランス不良による転倒や転倒に伴う骨折による痛みや、 痙縮による筋肉の痛みなど |
このような痛みに対しては周囲のサポートや装具の使用が重要です。姿勢を変えたり、運動しないために生じる筋力が低下したりなど、動かないことで生じる痛みが多いため、リハビリや自宅でのストレッチのほか、体を動かしやすくなる装具を積極的に利用しましょう。
痛みをやわらげるための対処法

痛みが出る原因は前述した通りですが、原因に対して必要な対処方法は異なります。
・薬物療法(痛み止め・神経用薬など)
・リハビリテーション(運動療法・ストレッチ)
・再生医療や先進的な治療法の選択肢
・ご家族ができるサポート
脳梗塞後遺症の痛みに対しては医師をはじめとした医療チーム全体の連携が重要です。さらに、再生医療といった先進的な治療方法だけでなくご家族のサポートも大切なので、以下の内容をしっかりとチェックしましょう。
薬物療法(痛み止め・神経用薬など)
脳梗塞の後遺症による痛みに対して、薬物療法で痛みの軽減が期待できる可能性があります。具体的に使用される薬剤は、以下のとおりです。
・筋弛緩薬
・抗うつ薬
・消炎鎮痛剤
・神経障害性疼痛治療薬
それぞれの特徴は、表をご参照ください。
| 薬剤 | 期待できる効果 |
| 筋弛緩薬 | 痙縮や拘縮で固まった筋肉の緊張を落とすことで、鎮痛効果が期待できる。 痙縮による筋緊張が強いケースにはボツリヌス注射で緊張緩和効果が期待できる |
| 抗うつ薬 | 痛みの信号を脳に伝える物質の働きを調整することで、鎮痛効果に期待できる |
| 消炎鎮痛剤 | 健側の炎症や筋肉痛に対して有効となる可能性がある |
| 神経障害性疼痛治療薬 | プレガバリンなどの神経障害性疼痛治療薬は脳梗塞後遺症の 神経因性疼痛における神経の興奮抑制により、痛みの軽減に期待できる |
これらの薬剤を、患者さんの状況に合わせて慎重に検討していく必要があります。
リハビリテーション(運動療法・ストレッチ)
リハビリテーションで行うことは以下のとおりです。
・運動療法でバランスをとる練習や筋トレ
・筋肉・関節に対するストレッチ
これらのリハビリを通じて、痛みの緩和を目指します。
運動療法の目的は、障害により動かしにくくなった四肢を少しでも動かせるようにすることと、健側(正常側)の筋力低下を防ぐことです。筋肉や関節の機能を少しでも維持することで、固まることによる痛みの軽減が期待できます。
ストレッチも同様に、筋肉や関節の機能維持に重要です。運動療法では動かしきれない角度まで筋肉や関節を伸ばすことで、柔軟性の維持・向上につながります。
これらの運動療法とストレッチを継続的に行うことで、痛みの緩和に効果が期待できます。
再生医療や先進的な治療法の選択肢
脳梗塞後遺症の痛みに対して、従来では薬物療法やリハビリテーションが主流でした。しかし最近では再生医療を始めとした先進的な治療方法も増えてきました。
幹細胞を活用した再生医療やrTMS(反復経頭蓋磁気刺激)など、先進的な治療方法も選択肢として数えられます。日常生活に支障が出るほどの痛みに悩まされている場合は、検討しても良いかもしれません。
ご家族ができるサポート
脳梗塞の後遺症による痛みは、なかなか他人には理解されにくく、とても辛いことも多いでしょう。そんなとき、ご家族のサポートが非常に重要になります。
具体的には、以下のような支援が挙げられます。
・歩行や着替えなど日常生活の手伝い
・些細な変化に対する気づき
・リハビリのサポート
・服薬管理
これらの支援を家族が行うことで、患者様の日常生活が格段に楽になります。また、自分では気づきにくい症状を早期に発見し、適切な対応につなげることも可能です。
こうした肉体的な負担の軽減だけでなく、精神的な支えとしての役割も非常に大切です。患者様自身も、多くの困難や精神的な辛さを抱えることが多いため、ご家族の支えが大きな力となるでしょう。
自宅だけでは難しい?自費リハビリのすすめ

脳梗塞後遺症の痛みを軽減するうえでは、自費リハビリもおすすめできます。これは、患者様やご家族だけでの自宅リハビリには限界があるためです。
例えば、自宅でのリハビリで症状の改善が見られない場合、次に何をすればよいかわからず悩むこともあるでしょう。その点、自費リハビリでは脳梗塞に関する専門知識を持つスタッフから指導を受けられます。
・患者様の詳細な評価ができる
・評価を元にしたリハビリプログラムの立案ができる
・細かい日常生活動作の具体的な解決策を指導できる
・患者様やご家族だけではわからない客観的な変化に対応できる
これらの利点から、自費リハビリは非常に有効な選択肢と言えます。
さらに、症状の改善だけでなく、社会生活への復帰にもつながる点が重要です。自宅リハビリでは第三者との関わりがどうしても少なくなりがちですが、自費リハビリに通うことで第三者との交流や外出の機会が増え、社会復帰の助けとなるでしょう。
まとめ|脳梗塞後の痛みは我慢せず、まずは相談から
脳梗塞後遺症の痛みについてまとめました。ポイントは以下のとおりです。
・脳梗塞後遺症の痛みの原因は3つある
・痛みの原因に対する対処方法はそれぞれ異なる
・治療方法として自費リハビリという手段もある
脳梗塞後遺症の痛みは、脳梗塞による脳の損傷が原因であるため、改善が難しい場合も少なくありません。そのため、患者様だけでなくご家族への負担も非常に大きくなるのが現実です。
負担が重くのしかかるなかで、ご家族だけで悩みを抱えると精神的な負担も増し、さらに辛くなってしまうことがあります。そんなときは無理をせず、些細なことでもまずは自治体のサポート窓口やかかりつけの病院、または弊社のフリーダイヤルなどに相談してみてください。
この記事が、少しでも皆様の支えとなれば幸いです。


 0120-866-816
0120-866-816